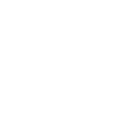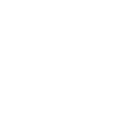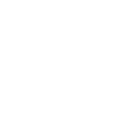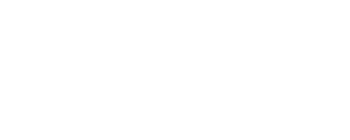難病で障害年金はもらえる?受給の条件から申請のポイントまで社労士が徹底解説
難病と診断され、日々の治療や体調不良で働くことが難しくなり、経済的な不安を抱えていませんか?
「まさか自分が障害年金をもらえるなんて…」
「難病は障害年金の対象になるの?」
と疑問に思っている方も少なくないでしょう。
この記事では、難病を抱える方が障害年金を受給できる可能性について、専門家である社会保険労務士がわかりやすく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、難病で障害年金を受給するための要件や、申請の際に特に重要となるポイントを知ることができます。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている方が受け取ることができる、国の公的な年金制度です。老齢年金と同様、国民の生活を支える大切なセーフティネットの一つです。
この障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
- 障害基礎年金: 国民年金に加入している方が対象で、主に自営業者や専業主婦(主夫)、学生などが該当します。障害の程度に応じて1級または2級が支給されます。
- 障害厚生年金: 厚生年金に加入している会社員や公務員などが対象です。障害基礎年金に上乗せされる形で、障害の程度に応じて1級、2級、または3級が支給されます。
障害年金は、病気の種類に関係なく、その方がどれだけ生活や仕事に制限を受けているかで判断されます。そのため、難病も当然、障害年金の対象となります。
難病で障害年金を受給するための3つの基本要件
難病で障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件: その難病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)が特定できること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日時点で、年金保険料を一定期間納めていること。
- 障害状態要件(認定基準): 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)において、国が定める障害の程度(障害等級)に該当する状態であること。
難病の認定基準は、その症状が多岐にわたるため、個別の病名で細かく定められているわけではありません。代わりに、その症状が「どの身体機能にどの程度の支障をきたしているか」が重要になります。日常生活動作の制限、就労の困難さ、症状の進行性などが総合的に評価されます。
難病の障害年金申請で最も重要なポイント
難病の障害年金申請では、病状が複雑で多岐にわたるため、その困難さを正確に伝えることが特に重要になります。
- 診断書の重要性: 審査で最も重要視される書類が「診断書」です。難病の場合、症状が日によって変動したり、複数の症状が同時に現れたりするため、医師に日常の困難さが伝わりにくいことがあります。診断書を作成してもらう前に、ご自身の病状や、それによって生じている日常生活の困難さを、具体的にメモにまとめて医師に渡すことをお勧めします。
- 「病歴・就労状況等申立書」の書き方: 発症から現在までの病気の経過や、日常生活・仕事の状況をご自身の言葉で伝えるための大切な書類です。難病の場合、診断がつくまでに時間がかかったり、症状が徐々に進行したりすることが多いため、この書類で詳細な経緯を伝えることが認定の鍵となります。
まとめ
難病と診断された方にとって、日々の治療に加え、経済的な不安は大きな負担となります。しかし、決して一人で抱え込む必要はありません。難病も障害年金の対象となり、症状や日常生活の状況によっては、経済的な支援を受けることが可能です。
症状が進行性であったり、寛解・増悪を繰り返したりする場合でも、諦める前に、まずはご自身の状況と照らし合わせてみてください。そして、少しでも不安を感じたら、専門家である社会保険労務士に相談してみることを強くお勧めします。
難病の相談窓口や情報収集について